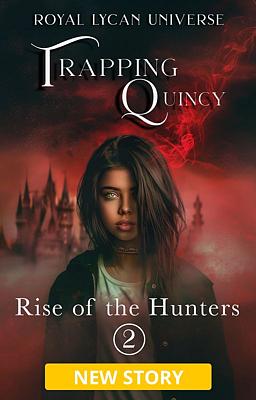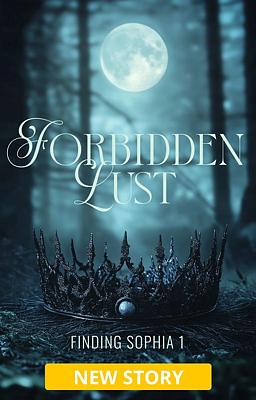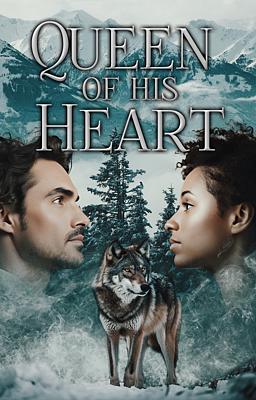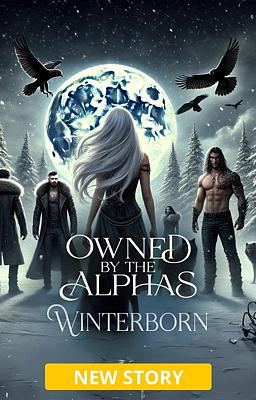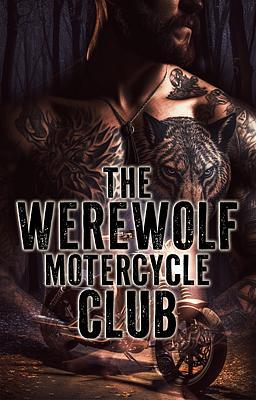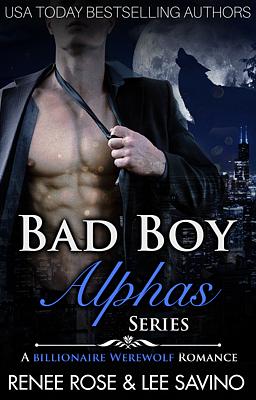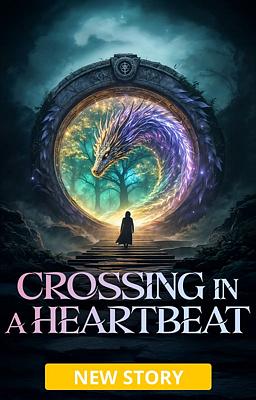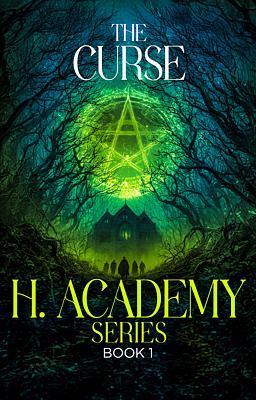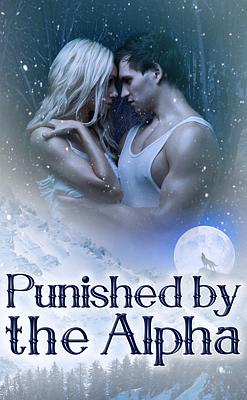Trapping Quincy
Nicole Riddley's Royal Lycans Universe has enchanted millions around the globe in ebook, print, audio and now TV.
Quincy St. Martin has spent her life as an outcast, enduring abuse in a werewolf pack that never accepted her. But when she finally escapes to California, she’s determined to start fresh—until she meets Prince Caspian Romanov, a powerful lycan who claims she’s his soulmate.
Torn between a new life of freedom and the dangerous allure of Caspian’s world, Quincy must navigate treacherous politics, family secrets, and her own transformation. As past and present collide, will Quincy find the strength to embrace her destiny?
Trapping Quincy is a captivating romance filled with passion, intrigue, and the fight for true love.
1: My Golden God
Quincy St. Martin