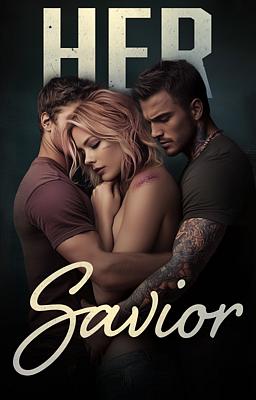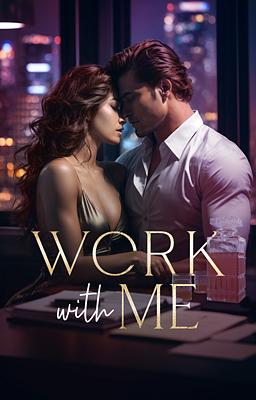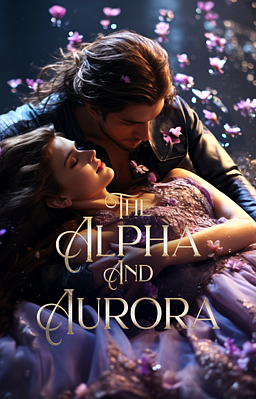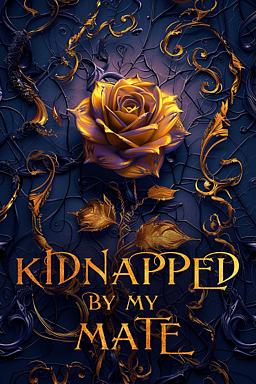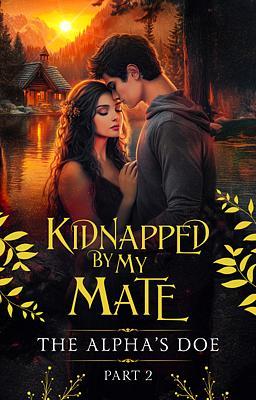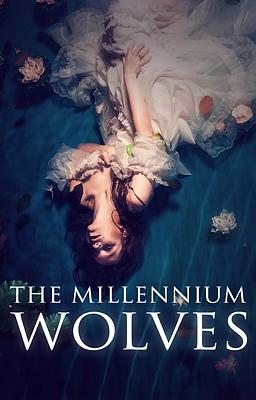His Lost Queen
"I can't survive without you. Do you understand me? There is no 'king thing' without you—there's not even a me without you."
Grayson never thought he'd lose Belle, but after months apart, he's desperate to win back her trust. Now the newly crowned King of the Supernatural, Grayson juggles royal duties while trying to reconnect with his estranged mate. But Belle's wounds run deep, and Grayson's attempts to explain what really happened are met with skepticism and fear.
Can Grayson prove his love is genuine and overcome Belle's doubts? Or will the secrets he's still keeping drive an insurmountable wedge between them? With enemies circling and a kingdom to protect, Grayson must find a way to heal Belle's heart or risk losing her—and everything else—forever.
Age Rating: 18+
1: Haunting Memories
Book 2: His Lost Queen
GRAYSON