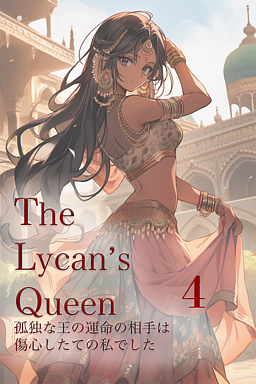
The Lycan's Queen 孤独な王の運命の相手は傷心したての私でした4
Author
L. S. Patel
Reads
🔥52.4M
Chapters
8
この巻は「The Lycan's Queen 孤独な王の運命の相手は傷心したての私でした3」からの続きです。
第15章
「味――わう」私はどうにか言葉にした。
アドニスの笑みが広がる。「そう、味わう。君の全身が私を求めている、可愛い人」
アドニスが近づいてきて、私はごくりとつばを呑み込んだ。もちろん、私は本能的にベッドの上のほうへと移動し、彼から離れた。
彼がほんの一瞬目を細めた。突然、私は獲物になったような気がした。アドニスは捕食者だ。彼が私を貪るように見つめている。
私が何も言ったり、したりできないうちに、彼は私の足首を掴んでベッドの下のほうへと引きずり下ろした。私は悲鳴を上げた。
「私から隠れる場所はどこにもない。君の欲望の匂いを嗅いだから、どうしてもそれを味わいたくなった」アドニスが私に覆いかぶさってきて、耳元で囁く。
どうしよう、私はこの人に殺される。私は自分の墓碑銘が頭に浮かんだ。「アドニスによってもたらされた 欲望によって死亡」
アドニスが顎から首筋へと軽く唇を這わせてきて、私の思考回路は切断された。ああ、どうして彼の唇はこんなにも気持ちいいの?
彼がさらにキスを続け、私は目を閉じた。私は、彼がまた私の唇にキスしてくれることを願った。意地悪なアドニスは、私の唇の近くまで迫りながら、唇にはキスしてくれなかった。
彼は自分が私に与えている影響に気づいていないのか、それとも気づいていて私の欲求不満を楽しんでいるのか、どちらだろう。
いいわ、彼が最初の一歩を踏み出さないなら、私から動いたっていいんじゃない? いらだちにうめきながら私は目を開け、アドニスの頭を掴んで唇を強く押しつけた。
アドニスが唸り声を上げ、唇を激しく押しつけて返して、私の上に乗ってきた。
ああ、彼の唇ってなんてステキなの! 私は彼の顔を引き寄せて、ますます激しくキスをした。
もしこれで死んだとしても、かまわない。だって、キスをやめたくなくなるような男とキスをしたのだから。
アドニスは私にキスするのをやめて、私の額に額を合わせた。二人で呼吸を整えている。
「いや、こういうのは期待していなかった」とアドニスは遂に言った。
「どうして? 女性から動いちゃいけないってこと?」
「君は私を怖がっていると思っていたから」
「どうしてそんなふうに思うのかしら? 私はあなたを怖がってなんかいないわ。それよりもむしろ……」私はその先の言葉を探した。
アドニスの視線が私を貫く。何かを探しているような目だ。
「それよりもむしろ?」と囁くような声で尋ねてくる。
「それよりもむしろ、魅かれてるわ」彼の唇が私の首筋に触れて、私は息を呑んだ。
「君は最高に美味しい、可愛い人」アドニスが私の首筋で唸る。
私は喘ぎ声を上げたくなかったが、アドニス相手に、それを止めるのは難しい。彼は首筋への攻撃をやめ、その唇を胸へと向かわせた。
彼のはしばみ色の目が私の目と合って、私は思わず息を止めた。これほど私への欲望と愛に満ちた目は、これまでに見たことがない。
アドニスは私を見つめ、唇を私の耳元へ寄せて囁いた。「息をして、可愛い人」
その言葉を聞いて、私はようやくふぅーっと息を吐いた。息を止めていたことに自分でも気づいていなかった。
「アドニス、何してるの?」
「君がしてくれていることに比べたら、何でもないよ」アドニスが私の耳にキスをする。
彼は起き上がり、私を起こしてくれたので、私は彼にまたがるような格好になった。正直なところ、私は彼のあまりの熱さに耐えられなかった。
「私にキスしようとする君は、信じられないほどセクシーだということを、君は知ったほうがいい」とアドニスは言った。
「気に入った?」
「ああ、とても。可愛い人。君は自分が思っている以上に自信があることを、自分自身にも私にも証明したね。自分に自信のある女性を見ることほどしびれることはない」そう言ってアドニスはにっこり笑った。
「あなたはいつも、私を夢中にさせる適切な言葉を知っているのね」と私は言った。
彼が何か答える前に、私は彼の首に腕を回して引き寄せた。
アドニスはくすくす笑いながら、私の腰に腕を回してきた。
「いくらでも逃げられると思うなよ、可愛い人。私は味わいたい」アドニスが囁きかける。
「もう味わったんじゃないの?」
「君への飢えはまだ満たされていない。私は君の体の最も秘めやかな部分を味わいたい」そう言ってアドニスは私の首筋にキスしてきた。
「ディミトリ?」と彼を呼ぶ声がした。
「無視しよう」アドニスはそう言って抱擁を解き、私の顔を指でなぞった。
私は喜びに震えた。
「ディミトリ? そこにいるのはわかってる! お願い」と、またあの耳ざわりな声がした。
ドアのところにいるのが誰かを、脳がゆっくりと認識したとたん、私の頭を曇らせていた欲望はきれいに消え失せた。
私はうめき声を上げてアドニスの膝から飛び降り、ドアを開けると、そこにはやはりサヴァナがいた。
彼女は、何か言いかけたところで、その視線が私に釘づけになった。腫れ上がった唇、乱れた髪、そしてアドニスのシャツを着た私は、おそらくひどい姿だっただろう。
「何かご用かしら?」私は尋ねた。
「どうしてあなたが彼のシャツを着てるの?」サヴァナが吐き出すように言う。
私は呆れ顔で天井を見上げた。「どうしてまだここにいるの? アドニスから、もうお呼びじゃないって言われたでしょ」
「何の用だ?」アドニスが私の上から言う。
「あの、あなたに聞きたくて……もし……」サヴァナは言いかけて、そこで視線を下のほうに向けた。
私は目を細めて彼女を見た。振り返ると、アドニスが上半身裸でそこに立っていた。この女は私の番いをチェックしていたんだわ。
私は唸りながらアドニスを押しやり、彼女とドアのあいだに体を差し入れた。これで私とサヴァナだけになった。
「私の番いをじろじろ眺めまわして恥ずかしくないの?」私は彼女を睨みつけた。
「彼は私の番いになるはずだったのよ」
「そうね、そうだったわね。でも、彼は私を見つけた。だから、もうあなたの居場所はないの。これが私からの最後の警告よ。私とアドニスのことは放っておいて。このフロアには二度と来ないで」私はぴしゃりと言った。
彼女に言い返す隙さえ与えず、私はくるりと向きを変えて中に戻った。そこにはアドニスが当惑しながら立っていた。
「何よ? スポーツブラ姿の私を肩にかつぎ上げておいて、元カノがあからさまにあなたをじろじろ眺めまわしているのを、私が怒っちゃいけないって言うの?」私は目玉を上に向けた。
「怒るとセクシーに見える。嫉妬が似合うね」アドニスがニヤニヤ笑っている。
「次はシャツを着て」と私は言って、ワードローブに別のシャツを探しに行った。
服を着替えて、私は部屋を出ていこうとした。アドニスと同じ部屋にいるのは、よい考えではない。
「どこに行くんだ?」
「わからないけど、どこか」と私は答えた。
「うーん、せっかくの時間が台無しになったな。別の日に味わうことにするよ」と言って、アドニスは私にウインクしてみせた。
「それとも、二度とないか……」と私は言い返した。
「私はすぐにそれを手に入れることを、二人とも知ってるだろ。私は欲しいものは手に入れる」アドニスが私を見つめてきた。抗うのが難しい。




