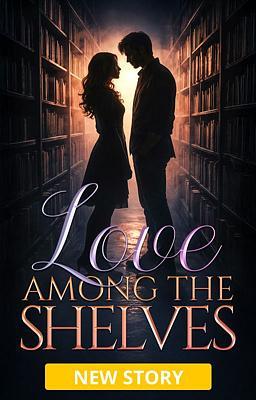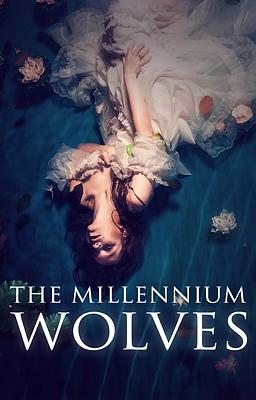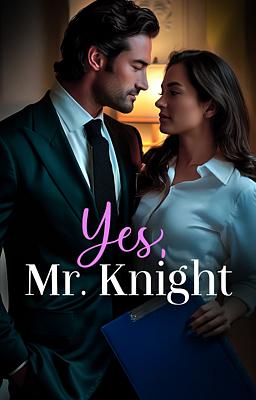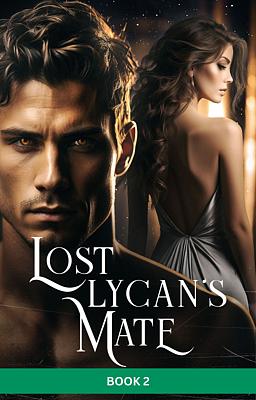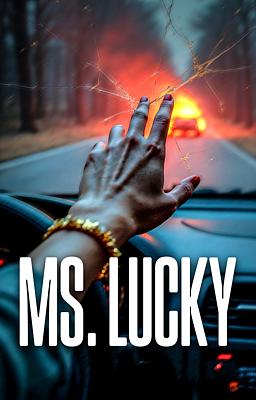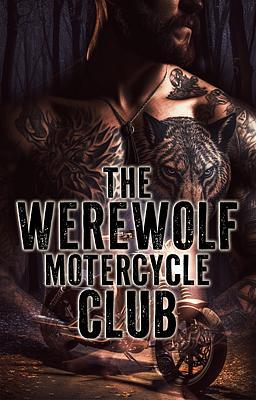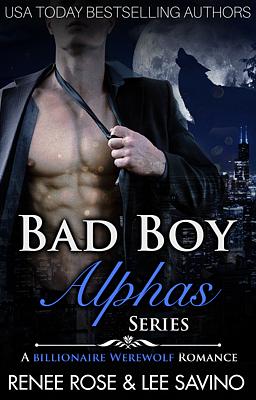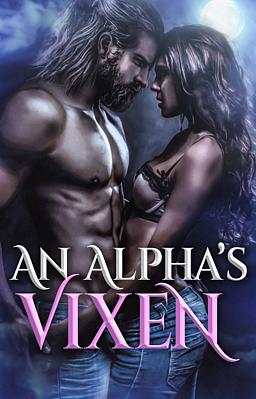Hated by My Mate: The Unwanted Luna
Alpha Wolfgang. He had the body of a god but the soul of the devil.
I should know. I was working at his birthday party the night I sensed my mate.
I was serving guests when suddenly my skin tingled. My heart pounded, and somehow I knew…
My destined mate was here. I turned to search for him. But when our eyes met, my heart stopped.
It was him. Alpha. Fucking. Wolfgang. And he looked furious.
He grabbed my face roughly, hatred in his icy eyes.
“Please, I know you want to reject me,” I trembled. ”Don’t worry. I’ll leave the pack.”
“You’re right,” he said, pressing his firm body against mine. “I don’t want you…”
“...But what makes you think I’ll let you leave me?”
Age Rating: 18+ (Murder)
Mortal Fears
AURORA