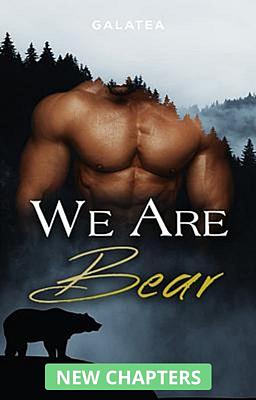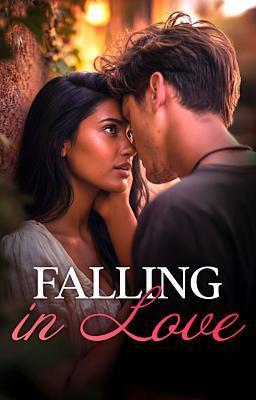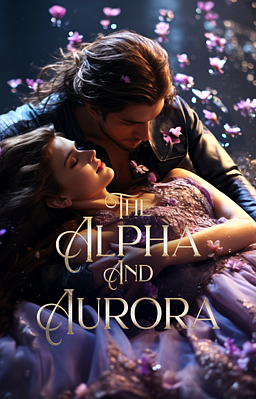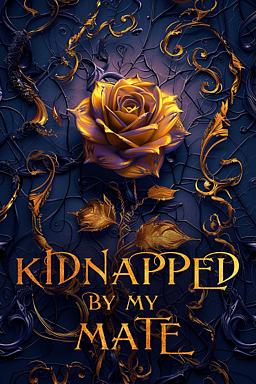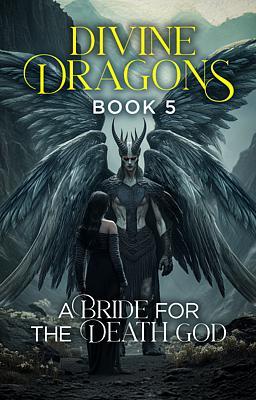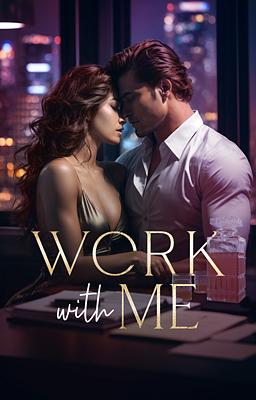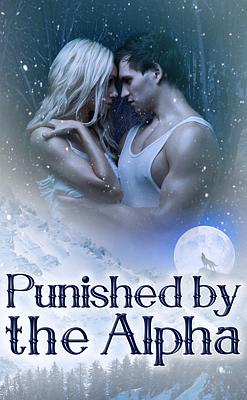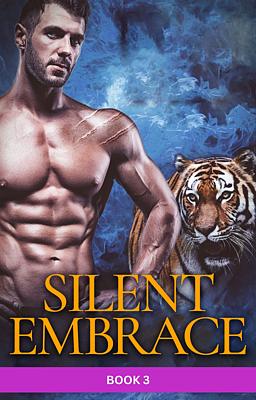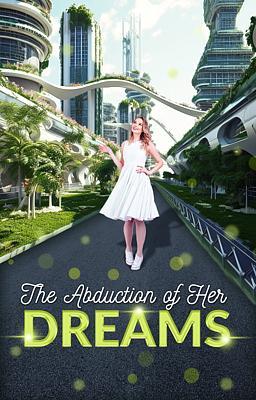Broken Queen
Her: A twenty-year-old werewolf, who has been chained to a table and tortured for years. Just as she’s about to get her revenge, the building explodes.
Him: The Alpha King of his pack, who is about to find her unconscious body in the wreckage and save her life.
As the light fades out, all I see are the stars sparkling above me. Suddenly, a pair of dazzling eyes cuts across my view, pulling me close as my senses dissipate. I hear his strong voice call to me as my vision goes dark…
"I know the pain you're in. But I promise you, you're safe. We can help each other through this."
Age Rating: 18+ (Torture, Extreme Violence/Gore)
1: Breaking Chains
ARIEL
ALEX