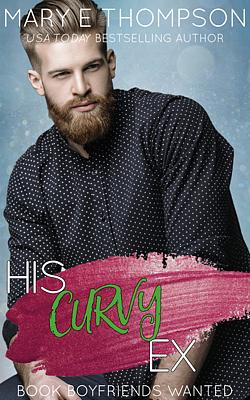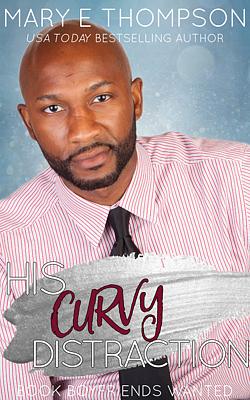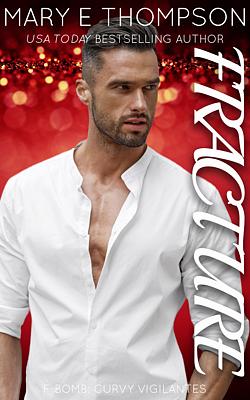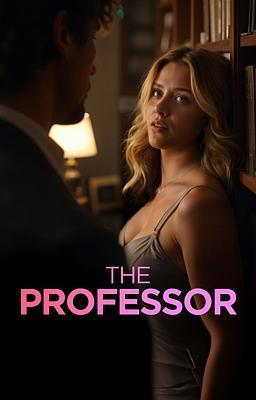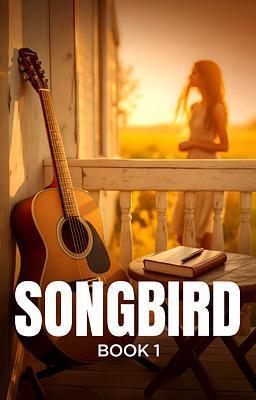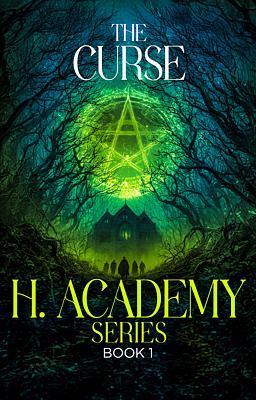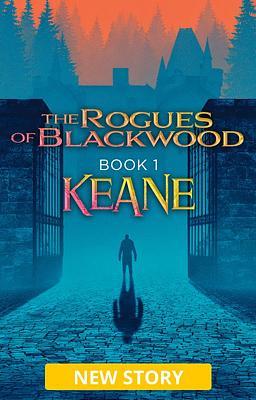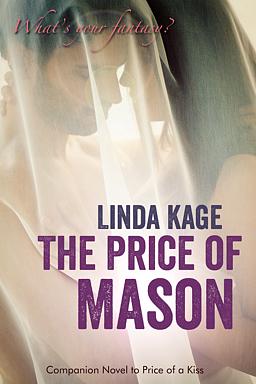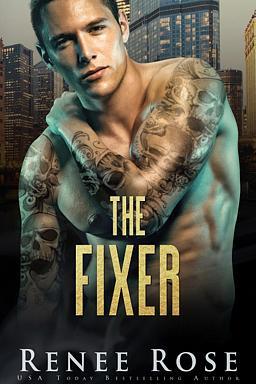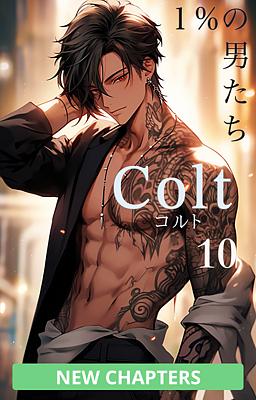
コルト 1%の男たち 10巻
Author
Simone Elise
Reads
🔥17.6M
Chapters
4
スカーレットは幼馴染のコーディーと面会するために刑務所を訪れた。
「ここには来るなと言ったはずだ」
「わかってる、ごめんなさい。ただ…会いたかったの」
そういうと笑ったコーディーと、少しだけ打ち解けて話せたスカーレットは、クラブとの関係を断ち切るべきだと話そうとした。しかしそのときに携帯が鳴り…
「今すぐクラブハウスに来てくれ」
「ちょっと取り込み中なんだけど…」
「サマーが気絶した。頼むよ、お前が必要だ」
対象年齢:18歳以上
見知らぬ者同士
スカーレット
時間は過ぎても、刑務所は変わらない。ガラス張りの面会室でコーディの到着を待ちながら、彼がここでどうやって生き延びているのか不思議に思った。確かに、救急救命室で醜い暴力を目の当たりにしたことはあるが、その暴力の中で「生き抜く」環境ではなかった。
コーディと違って、父とも違って。ようやく囚人たちが入ってきて、彼を見つけた。コーディ・ホーキンス。昔からの友人の一人だ。美しいと呼べる男がいるとすれば、それはコーディだった。彼独特の荒々しい感じがね。
私を見たコーディは、歓迎しがたいサプライズに顔を曇らせた。彼は座り、私たちは電話を手に取った。私が話し始める前に、コーディが私の言葉を遮った。
「ここには来るなと言ったはずだ」
「わかってる、ごめんなさい。ただ…会いたかったの」
彼はため息をつき、頭を振って笑みを浮かべた。歪んだ笑顔が私に向けられるたびに、うっとりとしてしまう。自分の感情をを必死に隠そうとした。コーディはそんな私を見たことがなかったはずだから。私たちは「ただの友達」だった。少なくとも私はそう思っていた。
「変わったな、トンボ」彼だけの愛称で私を呼んだ。
「そう? …まだ数ヶ月しか経ってないのに?」
「なんでかな。ずっと前髪あったか?」
無意識に目を伏せ、小さく笑った。今日はどうしたんだろう。刑務所のせいかもしれないし、長い間女性と会っていなかったせいかもしれない。だから、こんなに気があるそぶりをするのかしら。でも、そんな彼が好きでたまらなかった。
「いや、前髪はずっとあったわ。あなたが気づかなかっただけね」
「今まではな」
私たちは二人とも笑い合った。
デビルズ・ヘンチメンの子どもとして育った私とコーディは、いつもお互いを頼りにしていた。彼は会長であるランダルの息子で、私は副会長であるプリーストの娘だった。一緒にいると、ぴったりのコンビだった。
だけど、取り込みによってデビルズ・ヘンチメンがなくなった今、私たちの関係はどうなるのだろうと思った。
この機に、クラブとの関係を断ち切るべきだと思った。しかし、コーディを見て、あの歪んだ笑顔を見て、どうしたらいいのかわからなくなってしまった。
コーディにそのことを聞こうとしたとき、携帯が鳴った。
コルト
スカーレット、今すぐクラブハウスに来てくれ
コルト
急いでくれ
スカーレット
大事な用?
スカーレット
ちょっと取り込み中なんだけど…
コルト
サマーが気絶した
コルト
スコープが女を連れてきて、怪我をしてるみたいだ
コルト
頼むよ、お前が必要だ
スカーレット
わかったわ。すぐに行く
携帯を置いて、もう一度コーディを見つめた。まださよならは言いたくない。ため息しか出なかった。
「コルトか?」彼が尋ねた。
私は頷いた。コルトはコーディの刑期を短くしてくれた。だから私は彼にとても恩義を感じていた。それに、サマーは私にとってただの患者ではなくなっていた。それ以上の存在になっていた。彼女は私の大好きな友人だ。
コーディは頷いた。「行けよ。俺は大丈夫だ。こんなとこすぐに出て行くから—」
「ジャック・ロビンソンね」
「そうだ」
お互い微笑み合った。ガラスに手を置き、彼のぬくもりを感じたいと思った。でも、彼の言うとおりだ。そう長くはかからないだろう。コルトがどうにかしてくれたから。もう一度、その歪んだ笑顔を見た。
「またね、コーディ」
***
駐車場に車を停め、ロード・オブ・カオスのクラブハウスに急いだ。廊下に出ると、スコープは血だらけで、ドアの外を不安そうに歩き回っていた。私を見ると、すぐに寝室に案内してくれた。
「どっちもどこかおかしいみたいだ。どうにかしてくれ」
ベッドの横に膝をついたコルトは、すでに目を覚ましてマットレスの端に腰かけていたサマーに抱きついていた。
サマーの隣には、見たこともない女性がいた。意識がない。すぐに脈を確認した。脈は安定しているわね。
しかし、再びサマーを見ると、彼女はひどくショックを受けていた。震え上がり、汗をかいている。手にはビールを握っていた。
「オレンジジュースを飲ませてって言ったわよね」コルトに言った。
「ビールしかねぇんだよ。これが精いっぱいだ」
「二人とも、どっか行って。何かあったら電話するから」
コルトは頷いたが、立ち去る前にかがみ込み、サマーの頭にキスをした。この男からは見たことのない愛情表現だった。どのモーターサイクル・クラブの男もこんなことはしない。
彼とスコープが歩き出すと、コルトが小さくつぶやいたのが聞こえた。「人を集めろ、礼拝堂にだ」
ようやく一人になった私は、医療用バッグをベッドに置き、ポケットから懐中電灯を取り出した。そして、サマーのビールを取って脇に置いた。
「何があったの?」サマーの目にライトを当てて尋ねた。
「私は大丈夫。スコープがあの女性を抱いて入ってきたから、私はてっきり…彼らの仲間だと思ったの。あそこの人かと…何でもなかったわ。もう大丈夫よ」
そのままにしたくはなかったが、私の見立てでは、サマーは何ともないようだった。
立ち上がり、彼女の横にいる、まだ意識のない見知らぬ女性を診察し始めた。
サマーはビールを飲み続け、気持ちを落ち着かせていた。
「彼女が誰か知ってるの?」私は尋ねた。
「ううん。スコープはクラブの仕事で出かけていたんだけど、地下室で見つけたって言ってたわ」
眉をひそめた。「で? 今、彼のベッドにいるって言うの?」
サマーは肩をすくめた。どうせ私には関係ないことだと思いながら、診察を進めた。
しかし、サマーの友人として、もうひとつ質問があった。
「それで? あなたとコルトは?」
サマーはにっこり微笑んだ。
何か答えようとしたとき、ベッドの上の女性が体を動かした。
サマーはすぐにビールを置き、ベッドの枕元にいる私の横に立った。
なだめるように女性の髪をかきあげ、彼女の意識を集中させようとした。
「ねえ、あなた」私は言った。「名前を教えてくれる?」
彼女はまばたきをして、手をぶるぶる震わせた。そのとき、私は気づいた。
彼女の爪の下に、赤いチョーク状の物質があったのだ。看護師の経験から、その物質は赤リンの一種だと認識した。おそらくマッチ箱を剥がした時についたのだろう。つまり、考えられることはひとつしかない。
彼女はドラッグを扱っていたんだ。
どんな仕事かはわからないが、この女性に抱いていた同情は一瞬にして消えた。
コーディのことがあった後では、ドラッグの製造に関わっている人間はみんな私の敵だ。
この女も含めて。
ようやく彼女の口が開き、息の荒いささやき声で、名前が告げられた。私にとって、新しい敵の名前だ。
「私は…ヴァイオレットよ」
スコープ
この24時間はジェットコースターのようだった。
まず、レッド・クロウの裏切り。それから、この女…俺のことを知っているようなこの見知らぬ女…俺たちは奇妙な宇宙的繋がりを共有していた。すべてを受け入れるにはあまりに多くのことがあった。
彼女のそばにいたかった。そして彼女が言った「あなたを待っていた」という言葉の真意を知りたかった。タロットカードの意味も知りたかった。
今までの経験は全く役に立たなかった。すべて、わけのわからないことだらけだった。俺は空回りしていた。それに、悪魔が完全にわけがわからない状態だったから、全く役に立たなかった。
コルトがプールサイドのテーブルの前に一人でいるのを見つけた。
彼は思いつめていた。口を開く前から、それがわかった。
「一体何があったんだ、スコープ? すべてうまく行ったんだろ? 電話もメールも何もなかった。それに、攻撃を返せなんて命令もしていないだろ」
「そんな余裕はなかっ—」
しかし、コルトは怒りをあらわにして俺の言葉を遮った。
「スコープ、つながりは確かなものだった。レッド・クロウの会長は保証してくれたんだ。今回の取り込みは俺たちにとって完璧なものになるってな。なのに、お前がすべてを台無しにしたんだぞ。あのクラブはビジネスへの入り口になるはずだった。覚せい剤を作るビジネスだ。金が手に入るんだよ。お前のせいで、水の泡だ」
この男の口を殴るのを我慢するのに精一杯だった。拳を握りしめ、彼がくたびれるのを待つ間、俺の目はコルトを鋭くにらんでいた。
「終わったか?」そう尋ねると、彼は頷いた。「よし。率直に言うとな、コルト。もっとうまくやりたかったのなら、自分で行くべきだっただろ。運がなかったわけじゃない。最初から待ち伏せされてたんだ」
「レッド・クロウの野郎が俺たちを騙して、カモにした。それで今、あいつらが何をするのか何もわからない。奴らの母体はまだそこにある。だが、それがなんだってんだ? お前は妹の世話で忙しくて、仕事どころじゃなかったんだろ?」
「何言ってるんだ?」コルトは唸った。
「誰かがレッド・クロウに金を払って、俺たちを誘い込んだんだ。あるいは、お前が信頼している会長からの命令かもな。いずれにせよ、誰かが俺たちを狙っている。そこら中でな」
コルトはこのクソみたいな知らせを受け、しばらく考え込んだ後、礼拝堂に戻った。そこではみんなが待っていた。サントス、ランダル、プリースト、ジェイス、フライ、そしてあのちっこい見習い、ヘッファーまで。みんなだ。
動揺しながら後を追った。しかし、少なくともコルトの分厚い脳みそに何かを伝えることはできた。
「よく聞け」コルトは男たちに告げた。「女がいるなら、そいつのところに行け。一秒一秒を大切にしろ。一秒一秒をな。女はいないのか? なら、地元の店で好きな料理を注文すればいい。重要なのは、自分のために何かをすることだ。お前らがこれ以上生きながらえるか、神のみぞ知ることだからな。今日起きたことは始まりに過ぎない。戦争が始まるんだ。全員、覚悟しておけ」
ある者は頷き、血を流すことを望んでいた。ある者はうなだれて、恐れていた。
「今度、銃撃戦があったら、俺も招待してくれよ」
男たちは苦笑した。コルトは最後に大きく頷いた。
「行った。行った」
男たちが散り散りになったのを見て、今日はもう十分だと思い、階段に向かった。自分の部屋にいる見知らぬ女の様子を確認したかった。しかし、その前に—
「スコープ、待ってくれ」
「どうしたんだ?」俺は尋ねた。
「あの女のことだ」コルトが言った。「そいつはここにいられない。わかるな? もし無事なら、出ていかなくちゃならない。スパイかもしれないんだ。何者かわからない」
「なんだって、コルト。本気か?」
「俺が冗談を言うタイプに見えるか?」
「彼女はただの女の子だ。彼女は俺の、俺たちの助けが必要なんだ」
コルトは俺を見て、これが個人的な問題だと見抜いた。彼は一歩近づき、声を低くした。紳士的な野郎だ。
「お前があの女に…気持ちがあるのはわかってる」コルトは言った。「だけどな、俺たちは前にも女を侮ったことがあるだろ。どうなったか覚えてるか? 二度目はないんだ、スコープ。できたばかりのクラブだ。こんなときに、同じことを繰り返すってのか、スコープ」
「好きなだけ妄想してくれて構わないが、俺はあの子のために命をかけてるんだ。いいか?」
コルトは呆れたように見つめた。「彼女のことを何も知らないだろ」
一理ある。
しかし、そのとき、デジャブを覚えたことを思い出した。どういうわけか、俺は彼女を知っていたんだ。
「まあな」と私は言った。「だが、俺の妹の人生をめちゃくちゃにする前に、お前はあいつのことをどれだけ知ってたんだよ?」