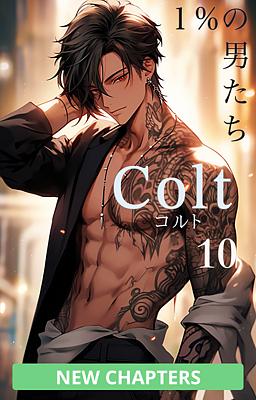
ソファに座り、テレビからは古い刑事番組の再放送が流れていた。でも私は夢の中にいた。コルトと私が…2回目に一緒になってから、彼のことが頭から離れなくなった。
彼の目、いたずらっぽく光るあの目。
彼の手が私の体をどうやって撫でたのか。
耳元で囁かれ、私はすぐに限界を超えてしまった。
あと…彼の胸のタトゥー。
今まで気づかなかったHの文字。見慣れたものだった。でも、モーターサイクル・クラブに囲まれて育つと、いつもタトゥーだらけだった。もうひとつのタトゥーは何だろう?
コルトと話したくなった。財布から携帯を取り出した。
ジョディ。
リチャード。
この人たちは誰?
そして気づいた。これは私の携帯ではないことに。
私は自分の番号を新しいメールに入力し、送信した。
最後に携帯を使ったのはいつだったか思い出そうとしていた。今日はまだスコープの家を出ていなかったから…昨日? スコープが模様替えのことをメールしてきたときかしら。私はホームストアにいて、それからスターバックスに行った。突然思い出した。そうだ、携帯をカウンターに置いて、ハンサムな男がいたんだ。
最悪。
私は「彼の」携帯をソファに置いた。
そして、これが何を意味するのか気づいた。 赤の他人が私の携帯を持って行ったのだ。
しまった。あの人たちはこのことを喜ばないはずだ。
私の携帯には、他人がアクセスできるはずのない情報が入っている。クラブの情報、メンバーや弁護士の電話番号、LCの仲間の情報。
そのとき、クラブのことなんかどうでもよかった頃、毎日何かをしていて忙しくて充実していた頃を懐かしく思った。
仕事というのはいつも、良いことも悪いことも含めて、自分の人生から気を逸らしてくれるものだが、今はそれも悪くないのかもしれない。
世界中のどんなドラッグも、これにはかなわない。
心臓が激しく高鳴り、寝室に近づくにつれ、頭が真っ白になった。あの女が寝室で待っている…
ヴァイオレット。それが彼女の名前だった。
昨夜、サマーが帰り際に教えてくれた。
彼女と距離を置こうと、俺はソファで寝ていた。こんな気持ちになるのは初めて…いや、シャーロット以来だ。
コルトの言う通り、彼女のことをほとんど知らなかった。しかし、馬鹿げた、そしてとんでもない理由で、この女性…ヴァイオレットは違うという予感がしていた。
もう一度、高鳴る心臓を落ち着かせようと気を引き締め、ドアをバタッと開けた。しかし、部屋を1度、2度、3度と見渡したが、誰もいないことに愕然とした。
気落ちした俺は、サマーの飲みかけのビールを手に取り、一気に飲み干した。誰もいない部屋でひとり。
本当に一人なのか?
突然、首筋に再び同じような疼きを感じた。振り向いて、バスルームのドアに立っている彼女を見ると、彼女は光に照らされて、まるで闇の中の天使のようだった。ヴァイオレットだ。
「ヴァイオレット、だな?」よろめきながら言った。彼女が近づいてきて、首を傾げながら俺を見つめている。
彼女は頷いた。「スコープ?」
彼女の唇から自分の名前を聞いた瞬間、魔法をかけられたように固まってしまった。
そのとき初めて、彼女が下着しか身につけていないことに気づいた。サマーたちが汚れた服を剥ぎ取ったのだろう。本能的に、シャツを脱いで彼女に渡した。ヴァイオレットがシャツを受け取るとき、指が触れ合うのを感じた。電気ショックのようだった。
ヴァイオレットの目が私と合った。「罪人、それとも聖人?」
困惑して、何と答えていいかわからなかった。そして彼女が俺の胸のタトゥーを指さしていることに気づいた。その文字の下には、それぞれマークがついている。奪われた命、救われた命。今のところ、救われたのは一人だけだ。サマーただ一人。
「罪人、と言ってもいいと思う」俺は言った。
「誰にとって?」
いったいどういうことなんだ? 女とこんなに深い話をしたことはなかった。シャーロットでさえ、この仕事で精神がすり減ることを話してくれなかった。
彼女は俺のシャツにひもを通し、はにかんだ笑みを浮かべた。「あなたには感謝しているわ、スコープ。私を救ってくれたもの」
どう答えていいかわからず、首の後ろを掻いた。「とりあえず、俺は、えっと、もう行く。くつろいでくれ」
しかし、俺が去ろうとしたとき、ヴァイオレットの顔が恐怖で真っ白になるのが見えた。初めて見た不安の表情だった。
「どうしたんだ?」俺は尋ねた。「俺に…いてほしいのか?」
「ずっと眠れなかった。一人じゃ眠れないの。もしよければ…今日だけ泊まっていかない? あなたの結婚生活を壊すつもりはないわ」
「結婚?」笑ってしまった。「信じてくれ。俺は独身だ」
「でも、あなたからは一生を誓った人のオーラが漂っているわ」
「えっと、」気まずくなり言葉をつづけた。「あのソファで一睡もできなかったんだ。じゃあ、あー、ベッドで寝ようか?」
俺たちはベッドを見つめ、どちらが先に動くべきか迷っていた。
結局、俺が先に横になり、ズボンは履いたまま、シーツの中に入らず上に乗った。しかしそのとき、ヴァイオレットがまだ立ったまま固まっていることに気づいた。
俺は立ち上がった。「どうしたんだ?」
「すごく久しぶりなの」
「誰かと同じベッドで寝るのは久しぶりか?」
「いいえ」彼女は言った。「ベッドで寝るのが、久しぶりで」
冷え切った心のどこかで、何かが大きくひび割れるのを感じた。
激情と混乱と怒りが一気にあふれ出てきた。
錆びついた建物のドアを引き開け、エリオットに出会う前からずっと気になっていたバーに入っていった。
そこはバイカーバーだった。昔はスコープが常連で、今でも彼とその仲間たちが立ち寄っているようだった。
「あの?」そう声をかけると、ビールで汚れた木が見えた。
しかしそのとき、オーナーであり、州で一番高齢のバーテンダーでもあるパパが、裏口のドアから顔を出した。もちろん、世界一高齢ではないけどね。
「会えて嬉しいわ、パパ」
彼は私の顔を見ると、目をさらに細めて私を受け止めた。
「サマー・ブリーズ」彼は足早に私のところへ向かってきた。そして、がっしりとした体で私を抱きしめ、最高のハグをしてくれた。それは、長い白髪のひげをたくわえた73歳の男性がくれる最高のハグだった。
「久しぶりだね」
「うん。最近はちょっと…忙しかったの」
「まだあのバカたちと一緒にいるのか?」
「いいえ」私はパパの言葉のチョイスに思わず笑ってしまった。
「それはよかった。どうしたんだ? いきなり」
「仕事を探しているの。もう一人バーテンダーが必要じゃない?」
彼は鼻で笑った。
「ここで40年バーテンダーをしているんだ。お前はパパのバーにいるんだろ。俺はパパだ」
私のしかめっ面を見たパパは、硬い表情を和らげた。
「まあ、いいさ」こう言った。「明日ここに来てくれ。売り上げが増えたら、考えてみよう」
信じられなかった。
「ありがとう!」私は思わず大声を上げ、もう一度彼に抱きついた。「約束するわ。今にわかるんだから、絶対に後悔させない」
「絶対にダメだ」コルトはテーブルの向こうから怒鳴った。
コルトの拳がテーブルを強く打ったせいで、スパゲッティのボウルが揺れた。
彼は大きく息を吸い込み、声のトーンを2段階ほど下げた。「仕事をする必要なんてない。まだ回復途中なんだ。仕事なんてするな」
自分の耳が信じられなかった。
彼は私をコントロールしようとしていた。私が自分の小さな世界に留まり、危険から遠ざかるように。この数カ月を振り返って、あんな目に合ったのに。私は笑うしかなかった。
危険はどこにいても同じだ。
「バイカーバーで働きたいだって? バイカーの老人どもにじろじろ見られたいのか? ケツをつかまれるのが好きなのか? 顔のしわで車の後部座席を作れるほどの皮の厚い男たちに? やってみろよ」
彼が私にそんなことを言うなんて信じられなかった。最近、私たちはとても仲が良かったから。なのに今、彼は毒を吐くように言葉を言い放っている。
「自立したいの」
「お金が必要ならやる。お前の前にダイヤモンドを投げつけることはできないかもしれないが、俺の女を養うことはできる」
屈辱的だった。
スコープがくれるお金だけでは足りなかった。今、彼氏は私が自分の面倒を見れないと思ってる。そして過去の私の結婚生活も侮辱している。
「金のためにタイトスカートを履いて踊るなんて大した女じゃないな」
「私はストリップなんてしていない!」思わず叫んだ。
私がスパゲッティのボウルを彼に投げつけると、彼は間一髪で身をかわした。
スパゲッティが壁に飛び散り、赤いトマトソースはたちまち白い壁を汚した。
私たちは混乱して目を見張った。
コルトは私が読み取れない視線を最後に、家を出て行った。